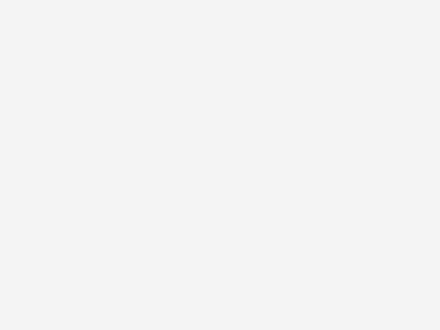相続遺産の独り占めを阻止するには
相続遺産の独り占めを阻止するために、相手はどのような理由で、遺産を独り占めすることができるのかについて、知っておく必要があります。
相続遺産の独り占めについては、遺言書がある場合と遺言書がない場合があります。
遺言書がある場合については、全部相続または全部遺贈は一つの例です。たとえば、Aは死ぬ前に、「私は死んだ後に、私の財産を全部Bに相続させてください」という遺言を作成したとします。その遺言を作成した後に、Aは死亡しました。BはAの遺言により、Aの財産を全部相続することになります。
または、Aは死亡する前に、「私が死亡した後に、私の遺産を全部Bに遺贈してください。」という遺言を作成しました。
その後、Aは死亡しました。Bは同じように、Aの遺言により、Aの財産を全部相続することになります。
遺言による財産の独り占めを避けるために、主に二つの方法があります。一つは遺言の効力を疑うことです。Bは遺言により、財産を全部相続することができるので、仮に遺言の無効を証明することができれば、Bの全部相続もそれにしたがって、無効になります。遺言が無効になる理由はたくさんあります。
たとえば、遺言方法の違反による無効(民法960条)、遺言の内容は公序良俗に反すれば、無効になること(民法90条)、意思無能力による遺言の無効(民法3条の2)などです。無効だけでなく、遺言の取消も主張することができます。たとえば、錯誤により、遺言を取り消すことができます(民法95条)。
取消された遺言は「はじめから無効であったものとみなす」(民法121条)。そのため、BはAの財産を全部相続することができなくなります。
遺言の無効または取消を主張できない場合に、遺留分の侵害を主張することができます(民法1042条)。
被相続人の遺贈と死因贈与も、相続の財産の価格の中に算入することができます。(民法1044条1項)。
しかし、贈与の対象により、算入する対象の時間的範囲が違うようになります。遺留分の算定はやや複雑であるので、専門家に任せるのをお勧めします。
また、遺留分侵害請求権の行使は、いつでもできるというわけではありません。
遺留分侵害請求権を有しても、相続開始時から10年間に行使しなければ、請求権は消滅します。
また、自分の遺留分が侵害されたと知った時から、1年間を行使しなければ、請求権は時効により消滅します(民法1048条)。
遺言書がない場合に、原則として、法定相続人は遺産分割協議(合意)で遺産を分割します(民法907条)。
その中の一人は遺産分割協議に応じないで、遺産を独り占める可能性があります。たとえば、Aが残した遺産は不動産甲だけだとします。
Aは子B、C、D三人を持っています。Aの子Bは甲を独り占めしたくて、CとDの遺産分割協議に応じません。
このような場合に、CとDは裁判所に審判分割を申し立てることが可能です(民法907条2項)。
相続問題に関して、悩んでいる方は早いうちに、専門家との相談をお勧めします。その理由は主に二つあります。
一つは、相続がしばしば時効の問題とかかわるので、遅くなると行使できなくなる権利があるからです。
もう一つは、時間が経てば経つほど、被相続人の財産はだんだん浪費されて減っていく傾向があるからです。
この場合に、被相続人の財産を保全する必要があります。具体的に、仮に被相続人の相続財産に貯金という項目があれば、被相続人の銀行口座を凍結するなどの方法があります。
神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市・芦屋市・西宮市・三田市を中心に大阪府などにおいて、皆さまからのご相談を承っております。
相続でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
実績豊富なプロフェッショナルが、皆さまのお悩みを解決いたします。